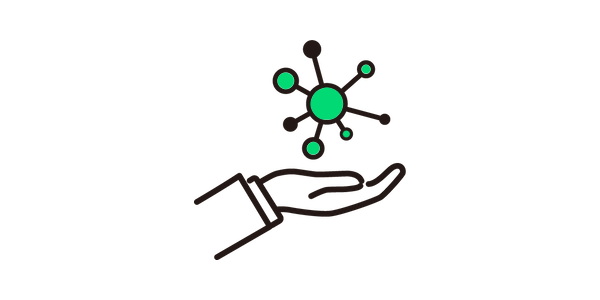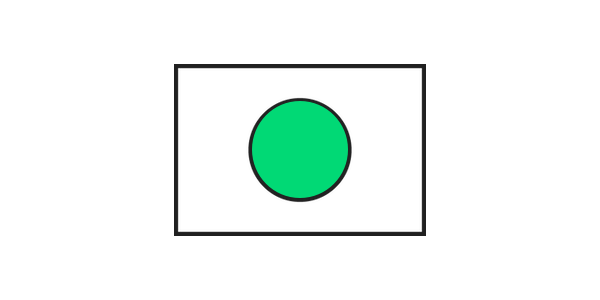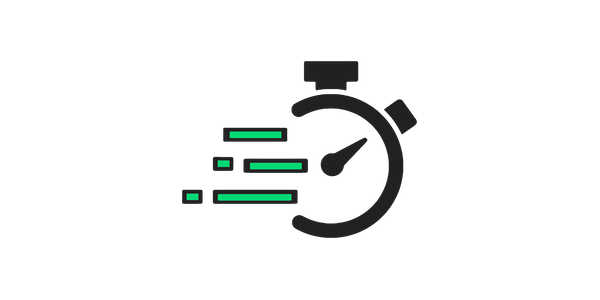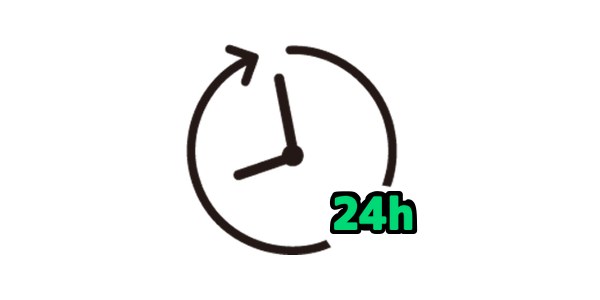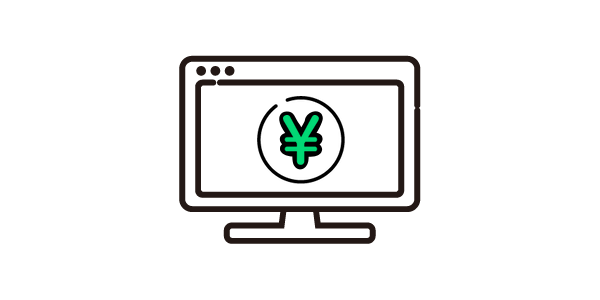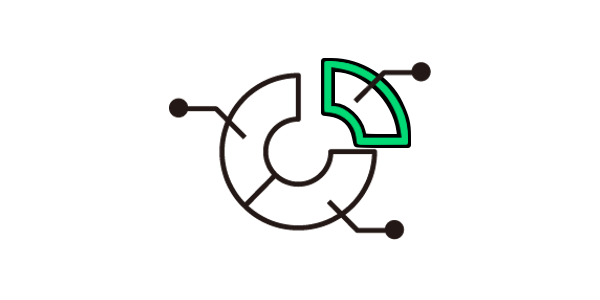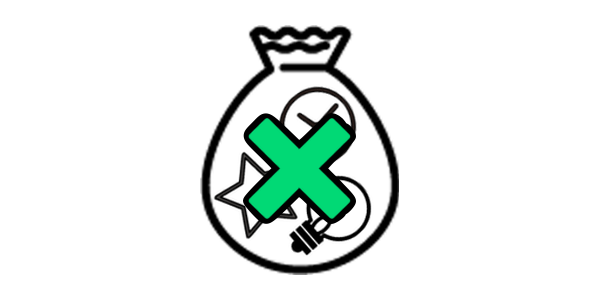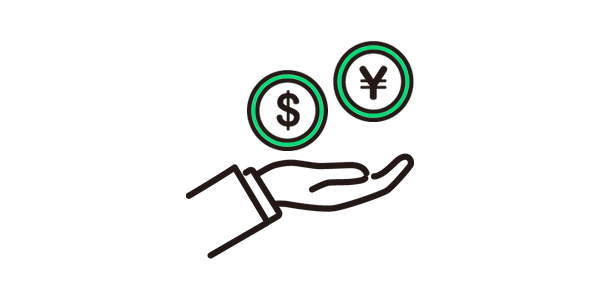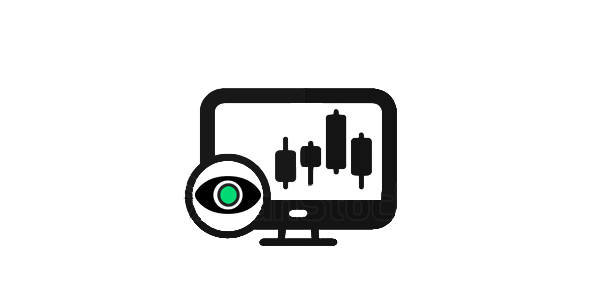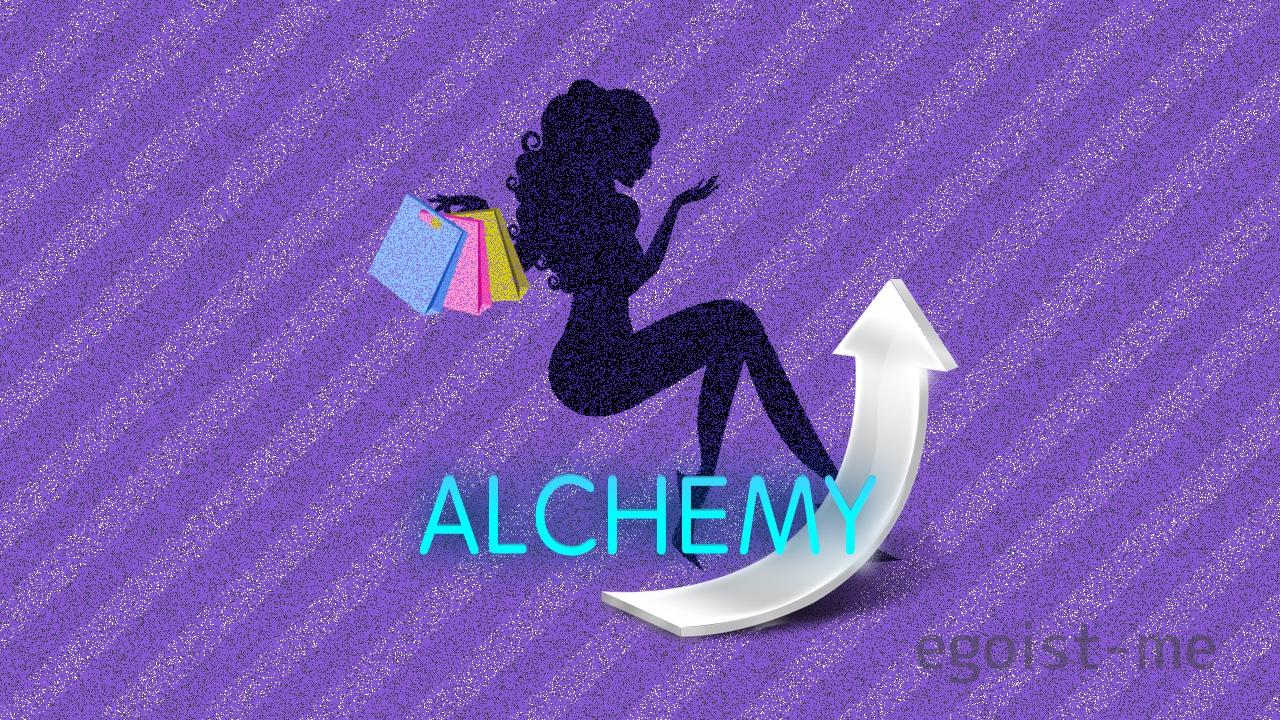LandFX UK Ltd.ではイギリスの金融ライセンスを取得、スプレッドは業界内でも極狭、スワップフリー口座もありマイナススワップを気にする事なく取引する事が可能、更にレバレッジ2000倍の設定があるだけではなく、プラスしてロスカット水準が0%のため有効証拠金がゼロになるまでロスカットされない事が魅力
Equinix社のNY4にサーバーを設置、レイテンシが低く相当優位な取引が可能、業界最高クラスの約定力と狭いスプレッドはスキャルピング取引にオススメ、また有効証拠金に応じたレバレッジ制限がない事もメリットの一つ
※既に口座をお持ちの方は、追加口座作成の際、紹介者番号欄に『8118642』をご入力ください
海外FX業者におけるシェア率No.1のFX業者!190か国以上1,000万人を超える顧客を有しグループ全体で5つの金融ライセンスを取得する巨大FX業者、ゼロカットシステムにてマイナス請求一切ナシ、出金拒否含め運用トラブルほぼナシの顧客満足度の高いスタイルが魅力

全額信託保全による絶対的安心運用/極狭スプレッド/99.9%の約定力/ゼロカットシステムによるマイナス請求ナシ/ストップレベルゼロが可能にする超短期取引等々、総合的に全てがトップクラスで理想的な取引環境が魅力